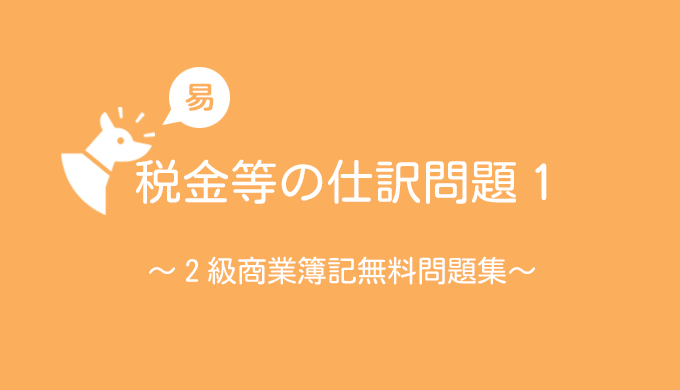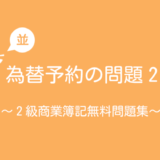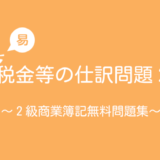問題
次の各取引の仕訳を示しなさい。ただし、使用する勘定科目は次の中から最も適切なものを選ぶこと。
| 現金 | 普通預金 | 当座預金 | 定期預金 |
| 仮払法人税等 | 未払金 | 未払法人税等 | 租税公課 |
| 追徴法人税等 | 受取利息 | 受取配当金 |
①固定資産税¥120,000について納税通知書を受け取るとともに、第1期分¥30,000を現金で支払った。
②上記①の固定資産税につき、第2期分の¥30,000を現金で支払った。
③普通預金口座に、普通預金に対する利息¥50,000から源泉所得税(20%)控除後の金額が入金された。
④当座預金口座に、配当金¥640,000(源泉所得税20%控除後)が入金された。
⑤定期預金(1年満期、年利率0.5%)¥1,000,000を銀行に預け入れていたが、本日満期となった。この満期額に、仮払法人税等に計上する源泉所得税(20%)控除後の受取利息手取額を加えた金額を、さらに1年満期の定期預金として継続した。
⑥過年度に納付した法人税について追徴の指摘を受けた。なお、この追徴に関する要納付額¥100,000については現時点でまだ納付していないため負債として計上する。
解答
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 租税公課 | 120,000 | 現金 | 30,000 |
| 未払金 | 90,000 | |||
| ② | 未払金 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
| ③ | 普通預金 | 40,000 | 受取利息 | 50,000 |
| 仮払法人税等 | 10,000 | |||
| ④ | 当座預金 | 640,000 | 受取配当金 | 800,000 |
| 仮払法人税等 | 160,000 | |||
| ⑤ | 定期預金 | 1,004,000 | 定期預金 | 1,000,000 |
| 仮払法人税等 | 1,000 | 受取利息 | 5,000 | |
| ⑥ | 追徴法人税等 | 100,000 | 未払法人税等 | 100,000 |
解説
①と②の取引
固定資産税や印紙税(収入印紙)などのように、費用となる税金は租税公課勘定で処理をします。
固定資産税の納税通知書は地方自治体が税額を計算して、納付時期にあわせて送付してくるものです。そこに記載されている税額を年4回に分けて納付(分割納付)することになりますが、1年分をまとめて納付(一括納付)することも可能です。
分割納付する場合は、納税通知書を受け取ったときに記載されている税額をすべて租税公課(費用)とし、税金の未払い分は未払金勘定で処理します。
その後、税金を納付したときにはその金額について未払金を取り崩していきます。
③と④の取引
利息や配当を受け取る際に、当社が支払うべき税金をあらかじめ銀行などが差し引き(源泉徴収し)、それを当社の代わりに国へ納めます。
源泉徴収された金額(源泉所得税)は法人税等の前払いとしての性格があるため、これを仮払法人税等勘定で処理をします。
④受取配当金:入金額¥640,000÷0.8=¥800,000
⑤の取引
【貸方】満期となった定期預金¥1,000,000を取り崩し、受取利息¥5,000(=¥1,000,000×0.5%)を計上します。
【借方】受取利息の源泉徴収税額¥1,000(=¥5,000×20%)は仮払法人税等とし、満期額¥1,000,000に受取利息の手取額¥4,000(=¥5,000ー¥1,000)を加えた金額を新たな定期預金として計上します。
⑥の取引
追徴とは、税金を追加で徴収することをいいます。法人税の追徴の指摘を受けた場合は、その金額を追徴法人税等勘定(費用)で処理します。
また、「現時点でまだ納付していない」とあるため、貸方は未払法人税等(負債)とします。