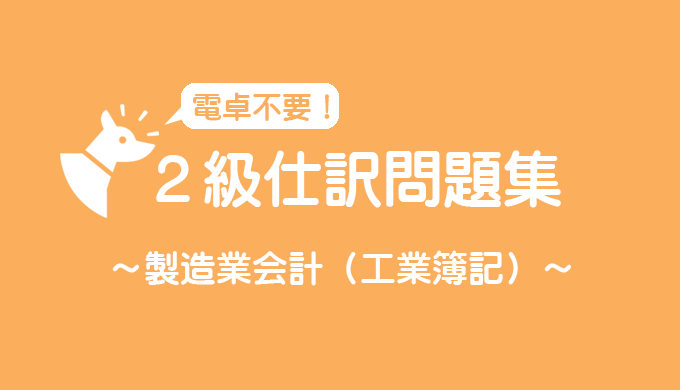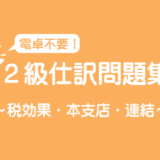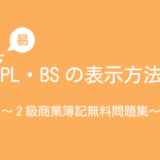| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 材料 | 1,000 | 買掛金 | 900 |
| 現金 | 100 |
【ヒント】
材料の購入原価は、購入代価に材料副費(付随費用)を加えたものとなります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕掛品 | 500 | 材料 | 700 |
| 製造間接費 | 200 |
【ヒント】
①材料を直接材料として消費したときは、その金額を仕掛品勘定へ振り替えます。
②材料を間接材料として消費したときは、その金額を製造間接費勘定へ振り替えます。
※材料を購入しただけでは製造原価になりません。消費してはじめて製造原価となる点に注意してください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 棚卸減耗損 | 50 | 材料 | 50 |
| 製造間接費 | 50 | 棚卸減耗損 | 50 |
【ヒント】
①材料の帳簿棚卸高は¥300です。「購入原価¥1,000ー消費額¥700=¥300」
②材料の帳簿棚卸高¥300と実際有高¥250との差額を棚卸減耗損とし、材料の帳簿の金額から控除します。
③棚卸減耗損は間接経費のため、これを製造間接費勘定へ振り替えます。
※製品の棚卸減耗はP/Lの項目(売上原価の内訳項目または販売費及び一般管理費)とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕掛品 | 2,000 | 賃金 | 3,000 |
| 製造間接費 | 1,000 |
【ヒント】
①直接労務費は仕掛品勘定へ振り替えます。
②間接労務費は製造間接費勘定へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 500 | 減価償却累計額 | 500 |
| 製造間接費 | 500 | 減価償却費 | 500 |
【ヒント】
工場の建物の減価償却費なので製造原価(製造原価報告書の項目)となります。減価償却費は間接経費なので、製造間接費勘定へ振り替えます。
※本社建物の減価償却費など、工場や製造活動に関係のない減価償却費は、販売費及び一般管理費(P/Lの項目)となります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 製造間接費配賦差異 | 150 | 製造間接費 | 150 |
【ヒント】
①製造間接費の実際発生額と予定配賦額との差異は製造間接費配賦差異で処理します。
②「実際発生額¥1,750(借方)>予定配賦額¥1,600(貸方)」の場合は、製造間接費勘定の貸方から製造間接費配賦差異勘定の借方へ振り替えることになります。
※本問では、実際発生額が予定配賦額よりも多く発生してしまったので不利差異ということになります。不利差異は製造間接費配賦差異勘定の借方に振り替えられるので借方差異という場合もあります。
※逆に「実際発生額<予定配賦額」となる場合では、実際発生額が予定配賦額よりも少なくて済んだということになるので有利差異となります。有利差異は製造間接費配賦差異勘定の貸方に振り替えられるので貸方差異という場合もあります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 800 | 製造間接費配賦差異 | 800 |
【ヒント】
①製造間接費配賦差異は年度末(決算日)において、1年間の金額を売上原価勘定へ振り替えます。
②不利差異(借方差異)の場合は、製造間接費配賦差異勘定の貸方から売上原価勘定の借方へ振り替えます。したがって、不利差異の場合は売上原価が増加します。
※逆に有利差異の場合は、売上原価勘定の貸方へ振り替えるので売上原価が減少します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 3,300 | 売上 | 3,300 |
| 売上原価 | 3,000 | 製品 | 3,000 |
【ヒント】
製品を販売したときは、その原価を製品勘定から売上原価勘定へ振り替えます。