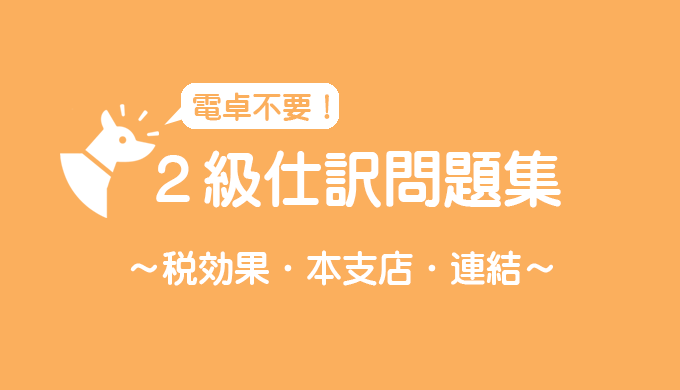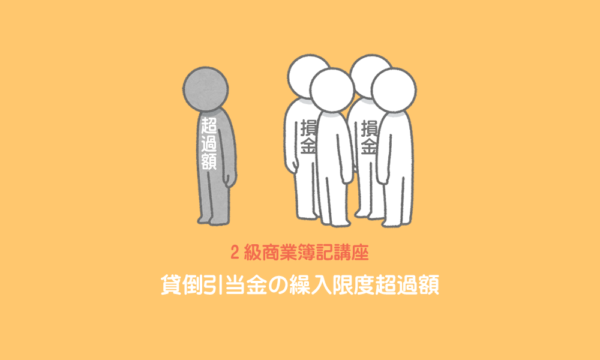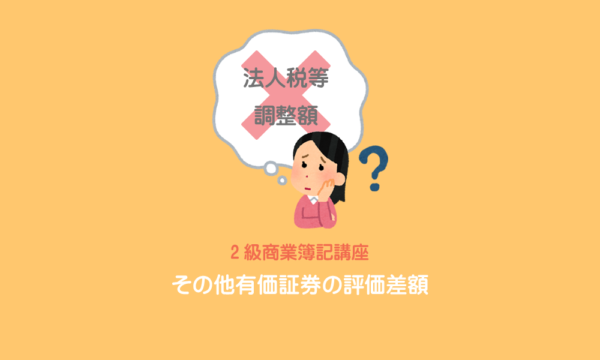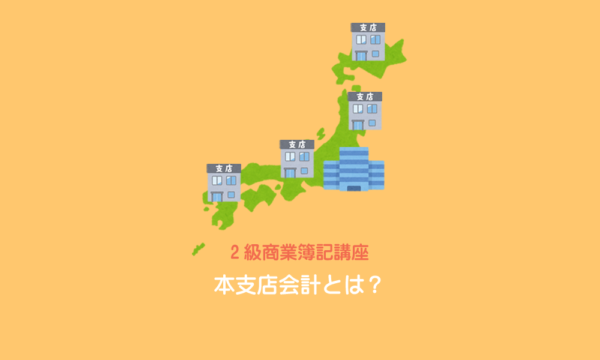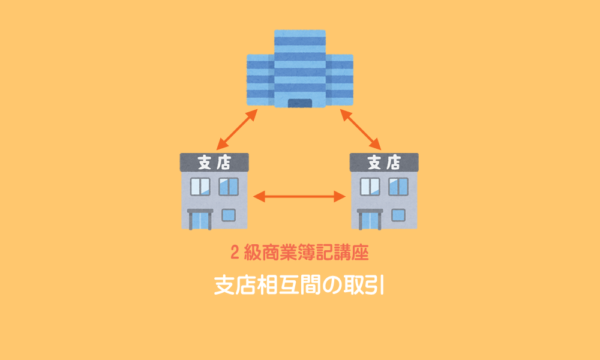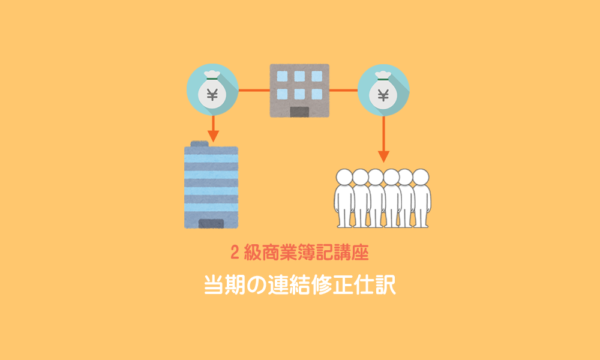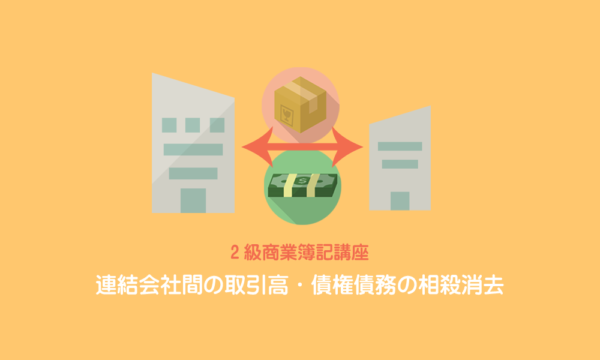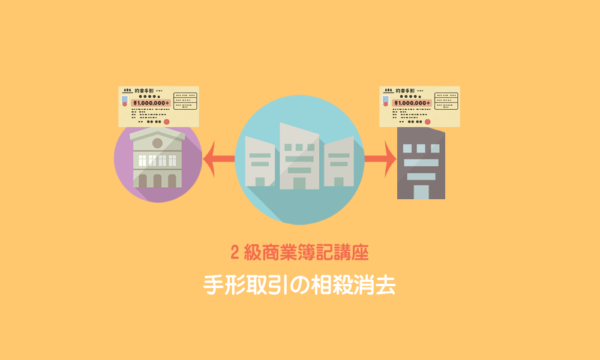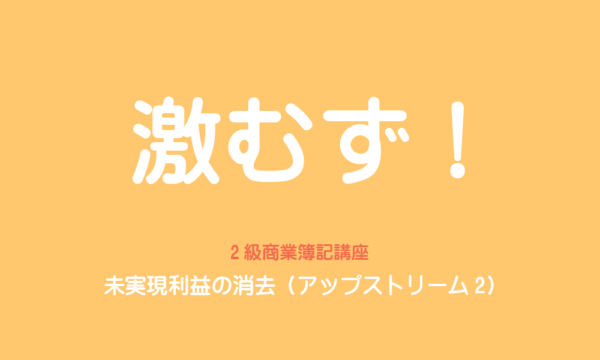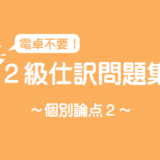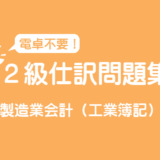| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 90 | 法人税等調整額 | 90 |
【ヒント】
①貸倒引当金繰入の一部が損金として認められない場合、課税所得(税金)が大きくなります。しかし、差異が解消されるときに課税所得(税金)が小さくなるので、この分だけ税金を前払いしたと考えることができます。
②この税金の前払分を繰延税金資産として処理し、貸方は法人税等調整額(法人税等のマイナス)とします。費用の前払い(前払費用)と同じように考えればOKです。
※金額は「¥300×30%=¥90」です。
【テクニック】
①まず、貸倒引当金の仕訳を考えます(貸倒引当金繰入500/貸倒引当金500)
②損益項目(貸倒引当金繰入)の反対側に「法人税等調整額」を記入します。
③その相手として借方に「繰延税金資産」を記入します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 90 | 繰延税金資産 | 90 |
【ヒント】
差異が解消したときは、税金の前払額である繰延税金資産を取り崩します。
※Q3-1の逆仕訳をすればいいだけです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 120 | 法人税等調整額 | 120 |
【ヒント】
①減価償却費の一部が損金として認められない場合、課税所得(税金)が大きくなります。しかし、差異が解消されるときに課税所得(税金)が小さくなるので、この分だけ税金を前払いしたと考えることができます。
②この税金の前払分を繰延税金資産として処理し、貸方は法人税等調整額(法人税等のマイナス)とします。費用の前払い(前払費用)と同じように考えればOKです。
※金額は「(会計上の減価償却費¥1,000ー税法上の減価償却費¥600)×30%=¥120」です。
【テクニック】
①まず、減価償却の仕訳を考えます(減価償却費1,000/減価償却累計額1,000)
②損益項目(減価償却費)の反対側に「法人税等調整額」を記入します。
③その相手として借方に「繰延税金資産」を記入します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等調整額 | 120 | 繰延税金資産 | 120 |
【ヒント】
差異が解消したときは、税金の前払額である繰延税金資産を取り崩します。
※Q3-3の逆仕訳をすればいいだけです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 100 | 繰延税金負債 | 30 |
| その他有価証券評価差額金 | 70 |
【ヒント】
①その他有価証券の評価差額(時価¥800ー取得原価¥700)に実効税率30%を掛けたものを繰延税金負債として計上します。
②評価差額から繰延税金負債を控除した金額をその他有価証券評価差額金とします。
※税法上は時価評価しないので時価が上昇すると売却益も増加する(税金が増加する)ため、これに係る税金の未払い分を繰延税金負債として計上します。
※その他有価証券評価差額金は損益計算書を通さずに直接、純資産に計上されるので法人税等調整額は使わずに、その他有価証券評価差額金を直接減額します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金負債 | 30 | その他有価証券 | 100 |
| その他有価証券評価差額金 | 70 |
【ヒント】
その他有価証券の時価評価は洗替法なので、翌期首に評価差額の再振替仕訳を行います。これにより会計上の簿価と税法上の簿価が同じになる(差異が解消する)ので税効果会計の仕訳も振り戻します。
※前期末の逆仕訳をすればいいだけです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | 30 | その他有価証券 | 100 |
| その他有価証券評価差額金 | 70 |
【ヒント】
①その他有価証券の評価差額(時価¥600ー取得原価¥700)に実効税率30%を掛けたものを繰延税金資産として計上します。
②評価差額から繰延税金資産を控除した金額をその他有価証券評価差額金とします。
※税法上は時価評価しないので時価が下落すると売却損が増加する(税金が減少する)ため、これに係る税金の前払い分を繰延税金資産として計上します。
※その他有価証券評価差額金は損益計算書を通さずに直接、純資産に計上されるので法人税等調整額は使わずに、その他有価証券評価差額金を直接減額します。
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支店 | 100 | 現金 | 100 |
【支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 100 | 本店 | 100 |
【ヒント】
【本店側】送金することで、本店の「現金」が減少します。これは本支店間の内部取引なので、相手勘定科目は支店勘定を使います。
【支店側】現金を受け取ることで、支店の「現金」が増加します。これは本支店間の内部取引なので、相手勘定科目は本店勘定を使います。
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支店 | 200 | 当座預金 | 200 |
【支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 200 | 本店 | 200 |
【ヒント】
【本店側】本店が小切手を振り出して支払ったので、本店の「当座預金」が減少します。支払ったのは支店の買掛金なので、相手勘定科目は支店勘定を使います。
【支店側】本店が立て替えて支払ったので、支店の「買掛金」が減少します。支払ったのは本店なので、相手勘定科目は本店勘定を使います。
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支店 | 300 | 売掛金 | 300 |
【支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 300 | 本店 | 300 |
【ヒント】
【本店側】本店の売掛金を支店が回収したので、本店の「売掛金」が減少します。回収したのは支店なので、相手勘定科目は支店勘定を使います。
【支店側】支店が現金で回収したので、支店の「現金」が減少します。回収したのは本店の売掛金なので、相手勘定科目は本店勘定を使います。
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 営業費 | 400 | 支店 | 400 |
【支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 本店 | 400 | 現金 | 400 |
【ヒント】
【本店側】支店が支払ったのは本店の営業費なので、本店側の「営業費」が増加(発生)します。支払ったのは支店なので、相手勘定科目は支店勘定を使います。
【支店側】本店の営業費を現金で支払ったので、支店の「現金」が減少します。これは本店の営業費なので、相手勘定科目は本店勘定を使います。
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支店 | 200 | 仕入 | 200 |
【支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 200 | 本店 | 200 |
【ヒント】
【本店側】手許にある商品が減少するので、本店は「仕入」の減少として処理します。相手勘定は支店勘定を使います。
【支店側】商品の原価が増加するので、「仕入」の増加(発生)として処理します。相手勘定は本店勘定を使います。
【大阪支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 神戸支店 | 100 | 現金 | 100 |
【神戸支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100 | 大阪支店 | 100 |
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
【ヒント】
【大阪支店側】神戸支店の買掛金を現金で支払ったので「現金」が減少します。これは神戸支店の買掛金なので、借方は「神戸支店」とします。
【神戸支店側】大阪支店が買掛金を立て替えて支払ったので、神戸支店の「買掛金」が減少します。支払ったのは大阪支店なので、貸方は「大阪支店」とします。
【本店側】支店分散計算制度では、支店間の取引について仕訳は必要ありません。
【大阪支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 本店 | 100 | 現金 | 100 |
【神戸支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100 | 本店 | 100 |
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 神戸支店 | 100 | 大阪支店 | 100 |
【ヒント】
【大阪支店側】神戸支店の買掛金を現金で支払ったので「現金」が減少します。本店集中計算制度では、各支店の帳簿には本店勘定のみが設けられる(ほかの支店勘定は設けない)ので、借方は「本店」とします。
【神戸支店側】大阪支店が買掛金を立て替えて支払ったので、神戸支店の「買掛金」が減少します。本店集中計算制度なので、貸方は「本店」とします。
【本店側】本店集中計算制度では、支店間取引を本店と支店との取引とみなして仕訳をします。本問の場合は、いったん大阪支店から現金を受け取って(現金100/大阪支店100)、神戸支店の買掛金を支払った(神戸商店100/現金100)と考えます。
【支店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 損益 | 400 | 本店 | 400 |
【本店の仕訳】
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支店 | 400 | 損益 | 400 |
【ヒント】
【支店側】支店の帳簿には繰越利益剰余金勘定がないので、支店の純利益を本店勘定へ振り替えます。
【本店側】支店勘定で支店の利益を受け入れ、それを損益勘定の貸方に記入することで、本店の純利益と支店の純利益を帳簿上で合算することができます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 損益 | 1,000 | 繰越利益剰余金 | 1,000 |
【ヒント】
本店の純利益¥600は損益勘定で算定され、また支店の純利益¥400はQ3-15で見たように支店勘定を使って受け入れています。最後に、当社全体の当期純利益¥1,000を損益勘定から繰越利益剰余金勘定へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 700 | S社株式 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 200 | ||
| 利益剰余金 | 100 |
【ヒント】
投資と資本の相殺消去の仕訳では、親会社の投資(S社株式)と子会社の資本(純資産)をそれぞれ減少させます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 700 | S社株式 | 800 |
| 資本剰余金 | 200 | 非支配株主持分 | 200 |
| 利益剰余金 | 100 |
【ヒント】
非支配株主(親会社以外の株主)の持分は「非支配株主持分」(純資産)に振り替えます。
※非支配株主持分の金額は「S社の純資産合計¥1,000×非支配株主の持分割合20%=¥200」です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 700 | S社株式 | 900 |
| 資本剰余金 | 200 | 非支配株主持分 | 200 |
| 利益剰余金 | 100 | ||
| のれん | 100 |
【ヒント】
①S社の純資産¥1,000のうち、親会社持分¥800(¥1,000×80%)に相当する金額は親会社の投資¥900(S社株式)と相殺消去します。
②両者の差額は「のれん」(無形固定資産)として処理します。
※仕訳上は貸借差額で計算しても構いません。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 700 | S社株式 | 750 |
| 資本剰余金 | 200 | 非支配株主持分 | 200 |
| 利益剰余金 | 100 | 負ののれん発生益 | 50 |
【ヒント】
親会社の投資がそれに対応する子会社の資本の金額を下回る場合(貸方に差額が出る場合)、その差額を「負ののれん発生益」(特別利益)として処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金当期首残高 | 700 | S社株式 | 900 |
| 資本剰余金当期首残高 | 200 | 非支配株主持分当期首残高 | 200 |
| 利益剰余金当期首残高 | 100 | ||
| のれん | 100 |
【ヒント】
開始仕訳では、連結株主資本等変動計算書における前期末までの金額(当期首残高)の修正も行う必要があるため、当期変動額(および当期末残高)と区別するために、純資産の科目には「当期首残高」または「期首残高」を付けます。
※ただし問題によっては付けない場合もあるので、試験では指示に従ってください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| のれん償却 | 10 | のれん | 10 |
【ヒント】
①借方に生じたのれんは連結貸借対照表の無形固定資産に表示し、残存価額ゼロ、直接法によって償却します。償却期間などは問題の指示に従ってください。
②のれんの償却額は「のれん償却」として処理します。
※金額は「のれん¥100÷10年=¥10」です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 200 | 非支配株主持分当期変動額 | 200 |
【ヒント】
①子会社の当期純利益のうち、20%は親会社に帰属しないもの(非支配株主に帰属するもの)なので、これを連結損益計算書の当期純利益から差し引くために、借方は「非支配株主に帰属する当期純利益」(当期純利益のマイナス)とします。
②この金額は非支配株主に帰属するものなので「非支配株主持分」(純資産)を増加させます。なお、株主資本等変動計算書における当期首残高(および当期末残高)と区別するために「当期変動額」を付けます。
※金額は「S社の当期純利益¥1,000×非支配株主持分割合20%=¥200」です。
※問題によっては「当期変動額」を付けない場合もあります。試験では指示に従ってください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取配当金 | 160 | 剰余金の配当 | 200 |
| 非支配株主持分当期変動額 | 40 |
【ヒント】
①親会社への配当は親子会社間の内部取引となるので、親会社の受取配当金¥160(子会社の配当金¥200×親会社の持分割合80%)と相殺消去します。
②利益剰余金のうち非支配株主の持分は、開始仕訳(投資と資本の相殺消去)において「非支配株主持分」へ振り替えています。そのため、S社の配当金のうち非支配株主に帰属する分¥40(子会社の配当金¥200×非支配株主の持分割合20%)は、利益剰余金(連結上は「剰余金の配当」)の減少を取り消して、非支配株主持分の減少として処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,000 | 売上原価 | 1,000 |
【ヒント】
①親子会社間の取引は連結修正仕訳によって相殺消去します。
②連結修正仕訳では連結財務諸表(連結損益計算書)上の科目を使うため、「売上」ではなく「売上高」とします。
③連結損益計算書では、売上原価の内訳は示さずに一括して表示するので、「仕入」(当期商品仕入高)ではなく「売上原価」とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 1,000 | 短期貸付金 | 1,000 |
| 受取利息 | 40 | 支払利息 | 40 |
| 未払費用 | 20 | 未収収益 | 20 |
【ヒント】
①親子会社間の取引によって生じた債権債務の残高は連結修正仕訳によって相殺消去します。
②親会社の「短期貸付金」「受取利息」「未収収益」と子会社の「短期借入金」「支払利息」「未払費用」をそれぞれ相殺消去します。
※連結修正仕訳では連結財務諸表(連結貸借対照表)上の科目を使うため、「未収利息」「未払利息」ではなく「未収収益」「未払費用」とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 500 | 受取手形 | 500 |
【ヒント】
連結会社間の手形の振出し(受取り)は、個別ベースでみると通常の支払(受取)手形ですが、連結ベースでみると何の取引も行われていないことになります。そこで、連結会社間の取引によって生じた「受取手形」と「支払手形」の期末残高を相殺消去します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 600 | 短期借入金 | 600 |
| 支払利息 | 50 | 手形売却損 | 50 |
【ヒント】
①手形の割引は連結ベースでみると、銀行へ手形を振り出してお金を借り入れる「手形借入金」(貸借対照表上は「短期借入金」)ということになるので、支払手形を取り消してこれを短期借入金とします。
②手形の割引に係る手形売却損は、連結ベース(短期借入金)でみると支払利息ということになるので、手形売却損を取り消してこれを支払利息とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
【ヒント】
①手形の裏書譲渡は連結ベースでみると、通常の外部からの手形の受取りということになります。連結上は、親会社の「受取手形」(の減少)と子会社の「受取手形」(の増加)が相殺されるため、連結修正仕訳の必要はありません。
※P社が外部から受け取った「受取手形」は外部との取引によるものなので、連結上も有効となります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 900 | 受取手形 | 900 |
【ヒント】
①P社が外部へ振り出した手形をS社が外部から裏書譲渡された場合、連結ベースでみると自身が振り出した手形を裏書譲渡によって回収したということになるので、この取引は自己振出手形の回収(支払手形の減少)ということになります。
②個別上、S社は「受取手形」(の増加)としているのでこれを取り消して、「支払手形」(の減少)となるように修正します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | 50 | 貸倒引当金繰入 | 50 |
【ヒント】
①連結修正仕訳では、連結会社間の取引によって生じた債権債務の期末残高を相殺消去します。
②連結上、連結会社間の売掛金残高は消去されるので、この売掛金に対して貸倒引当金が設定されることはありません。したがって、この売掛金に係る貸倒引当金の繰入を取り消します。
※金額は「売掛金残高¥1,000×5%=¥50」です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,200 | 売掛金 | 1,200 |
| 貸倒引当金 | 60 | 利益剰余金当期首残高 | 50 |
| 貸倒引当金繰入 | 10 |
【ヒント】
①連結修正仕訳では、連結会社間の取引によって生じた債権債務の期末残高を相殺消去します。
②前期に行った連結修正仕訳は帳簿上で反映されないので、当期に再び行う必要があります(開始仕訳)。前期の貸倒引当金繰入の修正額¥50は前期の利益(利益剰余金)の増加となるので、これを「利益剰余金当期首残高」とします。
③当期の貸倒引当金繰入の修正額は¥10((¥1,200ー¥1,000)×5%)なので、これを貸方に記入します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 200 | 商品 | 200 |
【ヒント】
①親子会社間で商品売買が行われた場合、その商品に含まれている利益は外部へ販売するまでは未実現となるので、連結修正仕訳によってこの金額を修正します。
②S社の期末商品のうち、P社から仕入れた商品に含まれる内部未実現利益¥200(=¥2,200÷1.1×0.1)だけ、期末商品が過大に計上されている(売上原価が過少となっている)ので、「売上原価」を増やすとともに「商品」を減少させます。
※連結修正仕訳では帳簿上の勘定科目ではなく、財務諸表の表示科目を使って仕訳を行うので、「仕入」ではなく「売上原価」、「繰越商品」ではなく「商品」を使います。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 利益剰余金当期首残高 | 200 | 売上原価 | 200 |
【ヒント】
①前期末の連結修正仕訳は個別会計上には反映されていないので、当期の連結財務諸表の作成にあたって、前期末までに行った連結修正仕訳を再度行う必要があります(開始仕訳)。
②S社の個別会計上は、未実現利益を含んだ金額で前期の利益(利益剰余金当期首残高)が計上されているので、これを取り消すために借方に記入します。
③この商品を当期に販売したことによって未実現利益が実現したと考え、当期の利益を増やすために貸方に売上原価を記入します。
※利益を前期から当期へ移動させるようなイメージです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 固定資産売却益 | 1,000 | 土地 | 1,000 |
【ヒント】
①土地を売却したことによる固定資産売却益¥1,000は、外部へ売却するまで未実現利益となるため連結修正仕訳によって消去します。
②連結上、親会社と子会社は1つの会社とみなすので、土地の売買取引はなかったと考えます。S社の個別B/S上の土地が¥1,000過大に計上されているため、これを取り消します。
※S社では土地の取得原価は¥6,000で計上されていますが、連結上はP社が外部から購入した金額の¥5,000とするべきです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 固定資産売却益 | 1,000 | 土地 | 1,000 |
| 非支配株主持分当期変動額 | 200 | 非支配株主に帰属する当期純利益 | 200 |
【ヒント】
①アップストリーム(子会社から親会社への売却)では、未実現利益の消去による利益の変動額について、非支配株主持分への影響額についても考慮する必要があります。
②アップストリームでは利益の減少額を非支配株主にも負担させるため、非支配株主持分を減少させます(借方の「非支配株主持分当期変動額」)。
③利益の減少額の一部を非支配株主に負担させるため、連結上の利益(親会社株主の利益)が増加します(貸方の「非支配株主に帰属する当期純利益」)。
※金額は「未実現利益¥1,000×非支配株主持分比率20%=¥200」です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | 50 | 貸倒引当金繰入 | 50 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 10 | 非支配株主持分当期変動額 | 10 |
【ヒント】
①貸倒引当金繰入の修正によって利益が増加するので、その利益の一部を非支配株主持分に振り替えます(貸方の「非支配株主持分当期変動額」)。
②利益の増加額の一部を非支配株主持分へ振り替えるため、連結上の利益(親会社株主の利益)が減少します(借方の「非支配株主に帰属する当期純利益」)。
※金額は「貸倒引当金の修正額¥50×非支配株主持分比率20%=¥10」です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 100 | 商品 | 100 |
| 非支配株主持分当期変動額 | 20 | 非支配株主に帰属する当期純利益 | 20 |
【ヒント】
①ダウンストリームの場合と同様に、期末商品に含まれている未実現利益¥100(=¥1,100÷1.1×0.1)を全額消去します。
②アップストリームでは利益の減少額を非支配株主にも負担させるため、非支配株主持分を減少させます(借方の「非支配株主持分当期変動額」)。金額は「消去した利益¥100×非支配株主持分比率20%=¥20」です。
③利益の減少額の一部を非支配株主に負担させるため、連結上の利益(親会社株主の利益)が増加します(貸方の「非支配株主に帰属する当期純利益」)。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 利益剰余金当期首残高 | 100 | 売上原価 | 100 |
| 非支配株主持分当期首残高 | 20 | 利益剰余金当期首残高 | 20 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 20 | 非支配株主持分当期変動額 | 20 |
【ヒント】
【1本目の仕訳】前期に消去していた未実現利益が当期に実現したので、①前期の利益を取り消して(借方)②当期の利益を増やします(貸方)。前期の利益を当期に持ってくるイメージです。
【2本目の仕訳】「①前期の利益を取り消した」ことによる非支配株主持分への影響です。前期の非支配株主持分を減らして、前期の連結上の利益(親会社株主の利益)を増やします。
※利益の減少額の一部を非支配株主持分に振り替えるので、逆に連結上の利益は増えます。減らし過ぎていた利益を戻してやるというイメージです。
【3本目の仕訳】「②当期の利益を増やした」ことによる非支配株主持分への影響です。当期の非支配株主持分を増やして、当期の連結上の利益(親会社株主の利益)を減らします。
※利益の増加額の一部を非支配株主持分に振り替えるので、逆に連結上の利益は減ります。