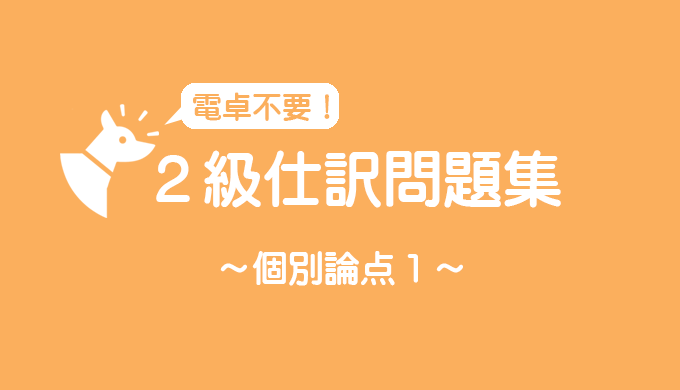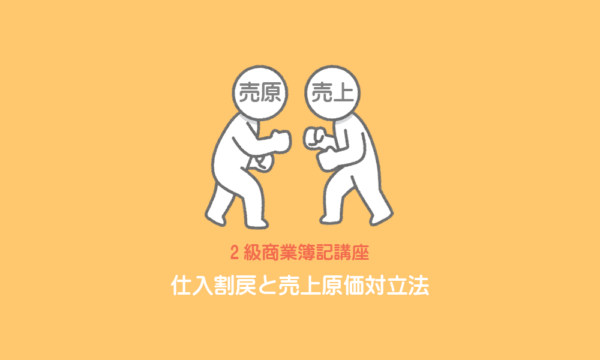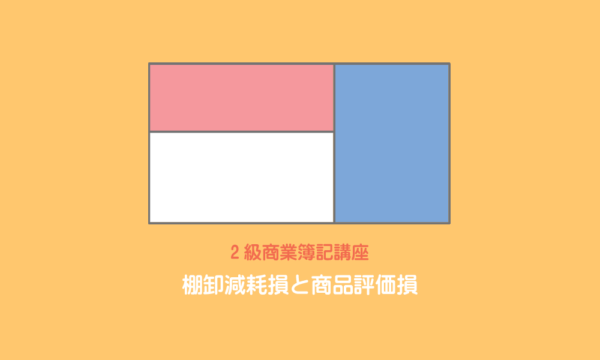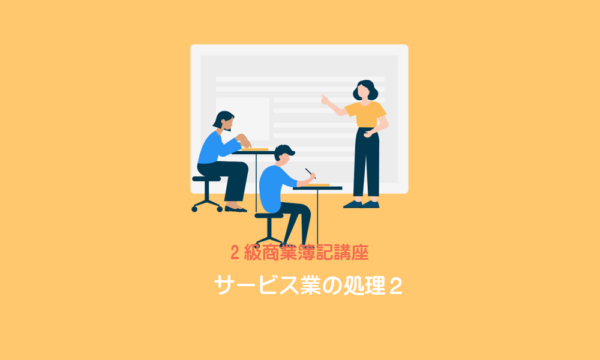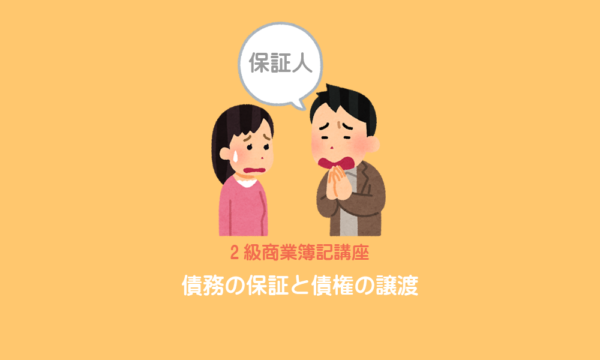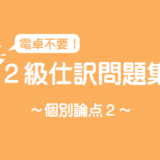- 仕訳に使用している勘定科目は日商簿記が公表している「標準的な勘定科目」を用いています。したがって解答の科目以外を使用しても許容される場合もありますが、試験では指定されたものを使用してください。
- 商品売買の記帳方法について指示がない場合は三分法を採用していると仮定してください。
- 仕訳が必要のない場合は「仕訳なし」としてください。
- 計算を容易にするために、数値を極端に小さくしています。
- 学習の管理にチェックシートをご活用ください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 900 | 買掛金 | 900 |
【ヒント】
①まず実際に行った仕訳を考えます【(借)買掛金1,000/(貸)当座預金1,000】
②次に正しい仕訳を考えます【(借)買掛金100/(貸)当座預金100】
③実際に行った仕訳(誤った仕訳)を正しい仕訳に修正するため、減らし過ぎている買掛金と当座預金をそれぞれ¥900増加させます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 500 | 当座預金 | 500 |
【ヒント】
携帯電話料金は通信費で処理します。
※連絡未達が判明した場合は、連絡が届いたものとして適正に処理をします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 200 | 買掛金 | 200 |
【ヒント】
小切手を振り出したとき(作成したとき)は、近い将来ほぼ確実に当座預金と買掛金が減少すると見込んでこれらを減少させますが、まだ小切手を渡していない以上、実際には当座預金も買掛金も減少する見込みがないのでこれを取り消します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 100 | 未払金 | 100 |
【ヒント】
広告宣伝費が未払いとなっているので未払金で処理をします。広告宣伝費は費用として実際に発生しているものなので、これをを取り消さないように注意してください。
※備品などの固定資産を購入した場合の未渡小切手も同様に未払金とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100 | 仕入 | 100 |
【ヒント】
3級で学習した返品の処理と同様に、仕入割戻を行ったときは商品を仕入れたときの貸借逆仕訳をすればいいだけです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 2,000 | 売上 | 2,000 |
| 売上原価 | 1,000 | 商品 | 1,000 |
【ヒント】
①商品を販売したときは売上勘定の貸方に売価で記入します(三分法と同じ)。
②さらに売上原価対立法では、販売した商品の原価(売上原価)を商品勘定から売上原価勘定へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
【ヒント】
売上原価対立法では、商品を販売したときに売上原価を商品勘定から売上原価勘定へ振り替えているため、決算において売上原価を算定するための仕訳は必要ありません。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 棚卸減耗損 | 200 | 繰越商品 | 200 |
【ヒント】
棚卸減耗損は期末商品の減耗を意味するものなので繰越商品勘定から控除します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 商品評価損 | 500 | 繰越商品 | 500 |
【ヒント】
商品評価損は期末商品の価値の低下を意味するものなので繰越商品勘定から控除します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
【ヒント】
期末商品の正味売却価額が原価を上回っている場合は何も処理はしません。
※「商品評価益」なるものは計上されません。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入 | 700 | 棚卸減耗損 | 200 |
| 商品評価損 | 500 |
【ヒント】
棚卸減耗損と商品評価損を売上原価に算入する場合は、これらを仕入勘定(売上原価勘定を使っている場合は売上原価勘定)へ振り替えます。
※棚卸減耗損は販売費及び一般管理費とする場合もあります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 契約資産 | 600 | 売上 | 600 |
【ヒント】
①「独立した履行義務」とは、商品 Aと商品Bの販売代金を別々に売上として計上するという意味です。したがって、履行義務を充足した(商品を引き渡した)商品 Aの代金¥600のみを売上とします。
②この時点ではまだ、顧客との契約から生じた債権となっていない(代金を請求する権利がない)ので、借方は契約資産とします。
※収益認識基準では、履行義務を充足した時に売上を計上します。
※代金を請求するのに、期日の到来以外に制約がない場合は売掛金を使いますが、期日の到来以外の制約がある場合は契約資産とします。
※問題文は長いですが仕訳自体は大したことないので、あまり難しく考えすぎないようにしましょう。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 1,000 | 売上 | 400 |
| 契約資産 | 600 |
【ヒント】
①商品Bについて履行義務を充足した(商品を引き渡した)ので、販売代金¥400を売上とします。
②この時点で、商品Aの代金(契約資産)も請求できる状態になったので売掛金へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 300 | 契約負債 | 300 |
【ヒント】
履行義務を充足する前に(商品を引き渡す前に)代金を受け取った場合は契約負債で処理をします。
※契約負債は「前受金」でも可。試験では指示に従ってください。
※3級で学習した前受金と同様に考えればOKです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 1,000 | 売上 | 900 |
| 返金負債 | 100 |
【ヒント】
①将来に割戻が予想される場合は、予想される返金額を差し引いた額をもって売上を計上します。
②予想される返金額は返金負債で処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 500 | 売上 | 450 |
| 返金負債 | 50 | ||
| 返金負債 | 150 | 未払金 | 150 |
【ヒント】
【上の仕訳(商品の販売)】考え方はQ1-16と同様です。
【下の仕訳(リベートの支払いに関する仕訳)】リベートの条件が達成された時点で、返金負債¥150(Q1-16の¥100とQ1-17の¥50)を取り崩します。返金は来月末に行うので、貸方は未払金とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
【ヒント】
サービスの提供が「一時点で充足される履行義務」である場合(1回限りでサービスの提供が終わるような場合)は、決算時には何も処理しません。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 500 | 役務収益 | 500 |
| 役務原価 | 300 | 仕掛品 | 300 |
【ヒント】
サービスの提供を行ったときに、前受金を役務収益へ振り替えるとともに、仕掛品を役務原価へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 1,400 | 役務収益 | 1,400 |
| 役務原価 | 700 | 仕掛品 | 700 |
【ヒント】
サービスの提供が「一定の期間にわたり充足される履行義務」である場合、サービスを提供する期間や進捗度に応じて収益(売上)を認識します。
したがって、先に受け取っている(支払っている)前受金と仕掛品の7割をそれぞれ役務収益・役務原価へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 600 | 役務収益 | 600 |
| 役務原価 | 300 | 仕掛品 | 300 |
【ヒント】
サービスの提供をすべて完了したときは、前受金と仕掛品の残額(3割)をそれぞれ、役務収益と役務原価へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 2,000 | 売上 | 1,400 |
| 契約負債 | 600 |
【ヒント】
①パソコン本体を引き渡す義務は「一時点で充足される履行義務」に該当するため、引き渡した時点でパソコン本体の対価¥1,400を売上に計上します。
②一方でサポートサービスは「一定の期間にわたり充足される履行義務」に該当するため、サービスを提供する期間や進捗度に応じて売上を認識します。したがって、この時点ではまだ売上を計上できないので、サポートサービスの対価¥600は契約負債とします。
※「契約負債」は「前受金」でも可。試験では指示に従ってください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 契約負債 | 300 | 売上 | 300 |
【ヒント】
①決算において、サポートサービスの提供開始日(10月1日)から決算日(3月31日)までの6か月間の金額を契約負債から売上へ振り替えます。
②金額は「¥600×6か月/12か月=¥300」です。
※「売上」は「役務収益」でも可。試験では指示に従ってください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 200 | 売上 | 200 |
【ヒント】
約束手形を振り出したときは支払手形で処理をしています。しかし、これが戻ってきたことにより手形代金を支払う義務がなくなるので支払手形を減少させます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 900 | 受取手形 | 1,000 |
| 手形売却損 | 100 |
【ヒント】
①手形の割引によって、受取手形¥1,000(額面金額)が減少します。
②割引料は手形売却損で処理をします。
③手取金(貸借差額)を当座預金とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手形 | 1,500 | 支払手形 | 1,500 |
| 支払利息 | 100 | 現金 | 100 |
【ヒント】
1本目の仕訳は、旧手形の減少と新手形の増加を表しています。借方の「支払手形」と貸方の「支払手形」は意味が異なるものなので相殺しないでください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 2,600 | 受取手形 | 2,500 |
| 受取利息 | 100 |
【ヒント】
手形の更改に伴う利息は新手形の額面に含める場合もあります。この場合、利息の分だけ新たに受け取る手形の額面金額の方が大きくなります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 不渡手形 | 3,200 | 受取手形 | 3,000 |
| 現金 | 200 |
【ヒント】
①不渡手形は通常の受取手形に比べて代金回収上のリスクが高いと言えます。そこで、通常の受取手形と区別するために、これを受取手形勘定から不渡手形勘定へ振り替えます。
②不渡手形の金額には、延長分の利息や償還に要した費用などの償還請求費用を含めます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 3,200 | 不渡手形 | 3,200 |
【ヒント】
不渡手形が回収不能となった場合は、通常の貸し倒れと同様に処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,100 | 不渡手形 | 1,000 |
| 受取利息 | 100 |
【ヒント】
①不渡手形を無事回収した場合は、不渡手形を減少させます。
②満期日以降の法定利息を受け取ったときは受取利息で処理をします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 不渡手形 | 2,300 | 当座預金 | 2,300 |
【ヒント】
①裏書譲渡や割引をした手形が不渡りとなった場合、当社に手形代金の支払い義務が生じるので、これを不渡手形として処理します。
②A社に支払った償還請求費用や延滞利息は後日B社に請求できるので、これらの金額は不渡手形に含めます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 営業外受取手形 | 4,000 | 土地 | 5,000 |
| 固定資産売却損 | 1,000 |
【ヒント】
商品以外のものを売却して約束手形を受け取ったときは営業外受取手形で処理をします。
※「受取手形」を使わないように注意してください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 備品 | 3,000 | 営業外支払手形 | 3,000 |
【ヒント】
商品以外のものを購入して約束手形を振り出したときは営業外支払手形で処理をします。
※「支払手形」を使わないように注意してください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 保証債務見返 | 300 | 保証債務 | 300 |
【ヒント】
①保証債務は”債務”とつくので、負債のようなものと考えてこれを貸方に記入します。
②借方には、保証債務の相手ということで”見返”を記入します。
※実際には「保証債務見返」と「保証債務」は、取引を忘れないように帳簿上で備忘記録を行うための対照勘定です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 300 | 現金 | 300 |
| 保証債務 | 300 | 保証債務見返 | 300 |
【ヒント】
①当社がA社に代わって債務を返済した場合、のちにA社に対してその代金を請求することができるので、A社に対する債権を未収入金などで処理します。
②保証していた債務が無くなったので、備忘記録していた保証債務見返と保証債務も取り消します。
※「未収入金」は「貸付金」や「立替金」でも可。試験では指示に従ってください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100 | 売掛金 | 100 |
【ヒント】
売掛金などの売上債権は、買掛金などの債務の支払いのために債務者の承諾を得た上で第三者へ譲渡することができます。この場合、これらの債権・債務を相殺させる仕訳を行います。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 400 | 電子記録債権 | 400 |
【ヒント】
電子記録債権を譲渡した場合は、電子記録債権を減少させます。
※所有している電子記録債権は、分割してその一部のみを譲渡することができます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 500 | 電子記録債権 | 600 |
| 電子記録債権売却損 | 100 |
【ヒント】
電子記録債権を譲渡(割引や売却)した場合、電子記録債権の帳簿価額と譲渡金額との差額を電子記録債権売却損で処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 750 | 電子記録債権 | 800 |
| 電子記録債権売却損 | 50 |
【ヒント】
電子記録債権を譲渡(割引や売却)した場合、電子記録債権の帳簿価額と譲渡金額との差額を電子記録債権売却損で処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 1,100 | 現金 | 1,100 |
【ヒント】
①「売買目的で」購入したとあるので、これを売買目的有価証券で処理します。
②金額は「10株×@¥100+手数料¥100=¥1,100」
※有価証券の購入に伴う付随費用は取得原価に含めます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 100 | 受取配当金 | 100 |
【ヒント】
①配当金は、株式配当金領収証を金融機関に持っていって換金してもらうことで受け取れます。したがって、これを受取配当金で処理します。
②株式配当金領収証は3級で学習した通貨代用証券なので、借方は現金とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 900 | 売買目的有価証券 | 1,100 |
| 有価証券売却損 | 200 |
【ヒント】
有価証券の帳簿価額(簿価)が売却額を上回る場合は、その差額を有価証券売却損で処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,200 | 売買目的有価証券 | 1,100 |
| 支払手数料 | 100 | 有価証券売却益 | 200 |
【ヒント】
①有価証券の帳簿価額(簿価)が売却額を下回る場合は、その差額を有価証券売却益で処理します。
②当座預金の金額(手取額)は、売却額の¥1,300から支払手数料¥100を差し引いた¥1,200となります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 1,200 | 売買目的有価証券 | 1,100 |
| 有価証券売却益 | 100 |
【ヒント】
売却時の手数料は、支払手数料で処理する方法のほかに、売却損益に含めて処理する方法もあります。
※手数料を売却損益に含める場合は、有価証券売却損に加算、または有価証券売却益から減額します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 有価証券評価損 | 500 | 売買目的有価証券 | 500 |
【ヒント】
①決算時の時価が簿価を下回っている場合には、貸方に売買目的有価証券を記入して簿価を時価まで減額します。
②簿価の切り下げ額は有価証券評価損として処理します。
※売買目的有価証券は決算時の時価で評価し、評価差額は当期の損益とします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 500 | 有価証券評価益 | 500 |
【ヒント】
①決算時の時価が簿価を上回っている場合には、借方に売買目的有価証券を記入して簿価を時価まで増やします。
②簿価の切り上げ額は有価証券評価益として処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | 9,600 | 現金 | 9,600 |
【ヒント】
①「満期保有で」とあるので、満期保有目的債券で処理をします。
※購入に係る付随費用(証券会社への手数料)は取得原価に含めます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 100 | 有価証券利息 | 100 |
【ヒント】
①保有している債券(社債や国債)の利息を受け取ったときは有価証券利息で処理をします。金額は「額面¥10,000×利率1.0%(半年分)=¥100」です。
※「受取利息」ではないので注意してください。
※金額は「額面¥10,000×年利率2.0%×6か月/12か月」で計算しても構いません。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕訳なし |
【ヒント】
子会社株式および関連会社株式は原則として時価評価を行わず取得原価で評価します。よって評価差額は生じないので、決算時の処理は「仕訳なし」ということになります。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | 97,000 | 現金 | 97,000 |
【ヒント】
「満期保有目的で」とあるので、満期保有目的債券で処理をします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,000 | 有価証券利息 | 1,000 |
【ヒント】
社債の利息を受け取ったときは、有価証券利息で処理をします。金額は「額面¥100,000×年利率1%=¥1,000」です。
※これは期中の仕訳となります(したがって、前T/Bに反映されます)。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | 1,000 | 有価証券利息 | 1,000 |
【ヒント】
①償却原価法(定額法)では、額面金額¥100,000と取得原価¥97,000との差額¥3,000を取得日から満期日までの期間(3年)にわたって月割で償却額を計算します。
¥3,000÷3年×1年(当期)=¥1,000
②償却額は、有価証券利息として計上するとともに満期保有目的債券の金額に加算します。
※これは決算時の仕訳となります(したがって、前T/Bには反映されていません)。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 3,500 | 現金 | 3,500 |
【ヒント】
売買目的有価証券、満期保有目的債券、子会社株式および関連会社株式のいずれにも該当しないような有価証券は「その他有価証券」で処理をします。
※「長期利殖目的」とは、売買目的有価証券のようにすぐに売却することは予定しておらず、また満期保有目的債券のように満期まで保有することも予定していない場合をいいます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券 | 500 | その他有価証券評価差額金 | 500 |
【ヒント】
①その他有価証券の簿価を時価まで切り上げるため、借方にその他有価証券を記入します。
②相手勘定をその他有価証券評価差額金とします。
※その他有価証券は決算時の時価で評価し、評価差額は「その他有価証券評価差額金」として純資産に計上します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | 500 | その他有価証券 | 500 |
【ヒント】
その他有価証券は翌期首において、時価評価の逆仕訳を行なって取得原価に振り戻します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 6,000 | その他有価証券 | 5,000 |
| 投資有価証券売却益 | 1,000 |
【ヒント】
その他有価証券を売却した場合は、取得原価と売却額との差額を投資有価証券売却損または投資有価証券売却益とします。
※時価評価したQ1-59のその他有価証券は、Q1-60において取得原価に振り戻されているということに注意してください。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | 300 | その他有価証券 | 300 |
【ヒント】
①その他有価証券の簿価を時価まで切り下げるため、貸方にその他有価証券を記入します。
②相手勘定をその他有価証券評価差額金とします(この場合、純資産のマイナスとなります)。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売買目的有価証券 | 5,000 | 当座預金 | 5,200 |
| 有価証券利息 | 200 |
【ヒント】
①「短期売買目的で」とあるので、取得原価は売買目的有価証券で処理します。
②直前の利払日の翌日から社債の購入日までの期間に係る利息はA社が受け取るべき利息なので、社債購入時にこの利息をA社に支払うことで調整します。このような利息を端数利息といいます。
③端数利息を支払ったときは、有価証券利息(のマイナス)として処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 4,300 | 売買目的有価証券 | 5,000 |
| 有価証券売却損 | 1,000 | 有価証券利息 | 300 |
【ヒント】
①直前の利払日の翌日から社債の売却日までの期間に係る利息は当社が受け取るべき利息なので、社債売却時にこの利息をB社から受け取ることで調整します。
②端数利息を受け取ったときは、有価証券利息として処理します。
③売却額¥4,000と社債の簿価¥5,000との差額が有価証券売却損となります。